
様々な新着情報をお届けします
メルマガ
2025.02.04
SNSでもお役立ち情報を配信しています!いいね・フォローをお願いします。
この時期流行するインフルエンザや感染性胃腸炎に負けないために、免疫力を高めていきたいですよね。
免疫力を高めるための食生活として、バランスよく食べることが第一ですが、ヒトの体のもとになるたんぱく質は免疫とも関係があります。
本日はたんぱく質がどのような栄養素なのかや体の中でのはたらきについてご紹介いたします。
たんぱく質とは、20種類のL-アミノ酸がぺプチド結合してできた化合物です。たんぱく質は他の栄養素から体内で合成できないため、ヒトが生きていく上で必ず摂取しなければならない栄養素です。
たんぱく質を構成するアミノ酸20種類のうち、9種類は不可欠アミノ酸 (必須アミノ酸) と呼ばれます。不可欠アミノ酸は体内で合成することができないため、食事から摂取する必要があります。
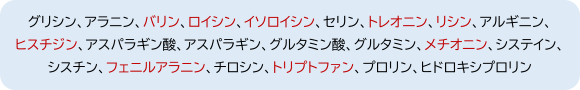
※赤字が不可欠アミノ酸を示す
3.1. 生体の構築材料
生体の水分を除いた重量の半分以上はたんぱく質です。毛髪や爪はケラチンからなり、結合組織にはコラーゲンが皮下全体に分布しています。また、筋肉はミオシンとアクチンからなっています。
3.2. ホルモン
ペプチドホルモン、アミノ酸誘導体ホルモンとして生体の恒常性維持に関与しています。
3.3. 抗体
免疫グロブリン (γ-グロブリン) は、抗体として生体防御に働いています。
3.4. 体液の調節因子
たんぱく質は巨大分子であるため、細胞膜を通過できませんが、細胞膜に浸透圧をかけることで細胞間の水分子の流れを調節しています。
たんぱく質摂取量の低下によって血漿たんぱく質が減少すると、血漿コロイドの浸透圧が低下し、血中の水分が組織間に漏出してむくみを生じます。
3.5. 体液の酸塩基平衡
たんぱく質や電解質が緩衝材として働くことで、体液のpHはほぼ7.4に維持されています。
3.6. 栄養素の運搬物質
ヘモグロビンは酸素、リポたんぱく質は脂質、トランスフェリンは鉄の運搬体として働きます。また、血清アルブミンは脂肪酸や陰イオンに対する親和性が高く、担体として働きます。
3.7. エネルギー源
たんぱく質は1 gあたり約4 kcalのエネルギーを生じます。糖質および脂質の摂取量が少ないときには、体たんぱく質合成よりもエネルギー源としての利用が優先されます。
たんぱく質は免疫において重要な抗体だけでなく、免疫細胞の材料でもあるため、この時期は特に、不足しないように摂取したいですね。次回は、たんぱく質の必要量についてご紹介いたします。
【参考文献】
| ● | 厚生労働省. 日本人の食事摂取基準(2025年版). Ⅱ各論, 1-2たんぱく質. 001316462.pdf (2025.01.14検索) |
| ● | 奥恒行, 柴田克己. 基礎栄養学 (改訂第5版). 株式会社南江堂, 2015. |
加齢に伴って減少する筋肉や筋力の維持に着目した試験はオルトメディコにお任せください。
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
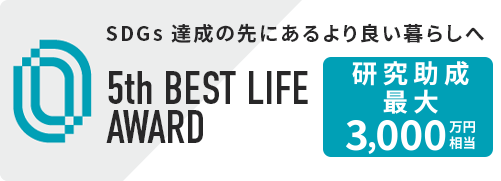 |
 |
 |
 |
 |
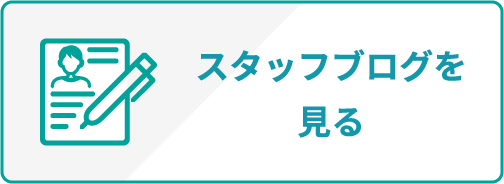 |
 |

ヒト臨床試験 (ヒト試験)
各種サポート業務等
各種お問い合わせは
お気軽にどうぞ
03-3812-0620 平日 | 9:00-17:00