
様々な新着情報をお届けします
メルマガ
2025.04.17
SNSでもお役立ち情報を配信しています!いいね・フォローをお願いします。
ヒトは空腹感を覚えると摂食行動を起こし、満腹感を覚えると摂食を止めます。この行動は間脳の視床下部外側野に存在する摂食中枢と視床下部腹内側核に存在する満腹中枢によって調節されています。
「食欲」と「摂取行動」に影響を与える因子にはいったいどのようなものがあるのでしょうか。
摂食中枢、満腹中枢に作用して食欲を調節する栄養素およびホルモンを下表にまとめました。
表1. 食欲を調節する栄養素およびホルモン
| 栄養素・ホルモン | 作用 | 分泌場所 |
|---|---|---|
| グレリン | 食欲促進 | 胃 |
| コレシストキニン | 食欲抑制 | 小腸 |
| ペプチド YY | 食欲抑制 | 小腸 |
| グルカゴン | 食欲抑制 | 膵臓 |
| グルカゴン様ペプチド-1 | 食欲抑制 | 小腸 |
| インスリン | 食欲抑制 | 膵臓 |
| レプチン | 食欲抑制 | 脂肪細胞 |
| アドレナリン | 食欲抑制 | 副腎皮質 |
| グルコース | 食欲抑制 | 肝臓 |
| 遊離脂肪酸 | 食欲促進 | 脂肪細胞、肝臓 |
料理の好ましいにおいや見た目、食感や舌触りなどの感覚は大脳皮質に伝えられ、食欲を亢進させます。また、口腔粘膜の刺激により食欲が継続しますが、咀嚼によりレプチンと似た働きをするヒスタミンが視床下部で分泌され、食欲が抑制されます。
過去に摂食し、好ましかったものに対しては食欲が亢進します。また、幼児期や小児期に習慣づけられた食経験は成長した後も食習慣として残り、食欲に影響します。
ほどほどのストレスでは食欲が亢進しますが、長期ストレスや強いストレスによって生体のダメージが大きくなると、消化管の働きが低下し、食欲も減退します。
寒冷環境では体温維持のためにエネルギー消費量が増加し、食欲が亢進します。反対に、温熱環境では、エネルギー消費量が少なく、脂肪蓄積が促進されるために脂肪細胞から分泌される血中レプチン濃度が高まり、食欲が抑制されます。
また、四季のエネルギー摂取量を調査した研究のメタアナリシスでは、冬や夏よりも春のエネルギー摂取量が多いことが示されました。
過食を防いだり、食欲を刺激したりなど、「食欲」自体をコントロールできると、無理なく健康増進に取り組めそうですね。
【参考文献】
| 1) | 灘本知憲. 基礎栄養学 (第5版). 株式会社化学同人, 2022. |
| 2) | 奥恒行, 柴田克己. 基礎栄養学 (改訂第5版). 株式会社南江堂, 2015. |
| 3) | Stelmach-Mardas M, Kleiser C, Uzhova I et al. Seasonality of food groups and total energy intake: a systematic review and meta-analysis. European journal of clinical nutrition. 2016;70:700-708. |
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
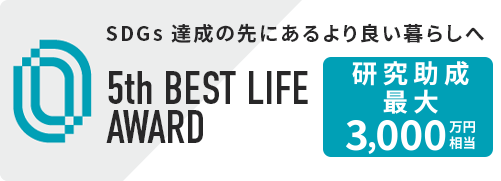 |
 |
 |
 |
 |
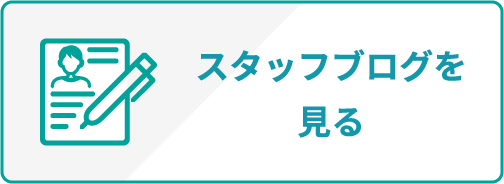 |
 |

ヒト臨床試験 (ヒト試験)
各種サポート業務等
各種お問い合わせは
お気軽にどうぞ
03-3812-0620 平日 | 9:00-17:00